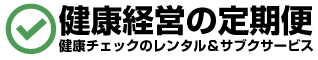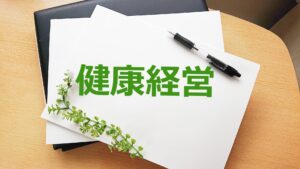目次
健康経営の核心は「社員の気づき」
健康経営というと、健康診断やイベント施策が注目されがちです。
しかし、本当に重要なのは——
✅ 従業員自身が「自分の体調変化」に気づける力
✅ 日常の中で“未病”に対して先回りできる感覚
いわゆる「健康リテラシー」の育成がカギになります。
健康リテラシーとは?
健康リテラシーとは、「健康に関する情報を入手・理解・活用し、自らの意思で健康を守る力」のこと。
📘 経済産業省による定義:
“生活習慣・環境・働き方・こころの状態など、自らの健康状態に対して意識を持ち、適切な判断や行動ができる力”
この力が高い人ほど、「未病」段階で適切な行動ができ、重症化を防ぐことができます。
“未病”に気づける社員は、企業の資産
たとえばこんな社員がいたら、どうでしょう?
- 朝から体がだるいと感じたら、無理せず早めに休む
- 食欲不振や軽い頭痛を放置せず、睡眠や食事を見直す
- 周囲にも「最近ちょっと疲れてない?」と声をかけられる
これこそが、「未病への気づき」がある社員像です。
こうした社員が増えると——
- 欠勤・病欠の減少
- チーム内の支え合い・対話の促進
- 健康リスクへの早期対応
といった好循環が生まれます。
健康リテラシーを高める職場づくりのポイント
✔ ①「気づき」を促す掲示物・リーフレット
- 未病や生活習慣病のセルフチェック表
- 季節ごとの健康管理ポスター(熱中症・冷え・感染症など)
- 「今日の体調は?」などのワンフレーズ掲示
✔ ② 日常的なヘルスコミュニケーション
- 朝礼や週次ミーティングで一言「最近の調子」チェック
- 上司や同僚同士で「気にかける文化」の醸成
- チャットツールに「健康トーク部屋」などの導入も有効
✔ ③ 計測習慣をつける機器の設置
- 血圧・体重・体脂肪など、手軽に測れる健康測定機器を設置
- 月1回の測定習慣を促す
- 自分の数値を記録して変化に気づけるようにする
健康リテラシー向上の効果(データより)
経済産業省の調査では、健康リテラシーが高い職場は以下の効果が期待されるとされています:
- 従業員の満足度向上
- 生産性の維持・向上(プレゼンティーイズムの抑制)
- 離職率の低下
- メンタルヘルス不調の早期発見
よくある質問(Q&A)
Q. 健康リテラシーは教育で高められるものですか?
A. はい、「情報提供+対話+習慣づけ」の3つの要素を組み合わせることで、徐々に高めることが可能です。定期的な健康セミナーやチーム内対話の機会も効果的です。
Q. 測定機器の設置は本当に有効?
A. “自分の体の状態を可視化”することで、「自分ごと」としての健康意識が高まりやすくなります。結果、未病の段階での気づきが早まり、生活改善行動へつながります。
まとめ|健康に気づける社員を育てよう
- 健康経営の土台は「健康リテラシーの高い社員」
- “未病”に気づく力が、企業の医療費削減や生産性向上につながる
- 日常の気づき、対話、計測習慣を職場に取り入れることで、自然に健康意識が育つ
従業員の“気づく力”は、組織の未来を支える力になります。