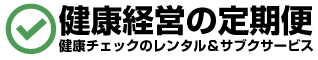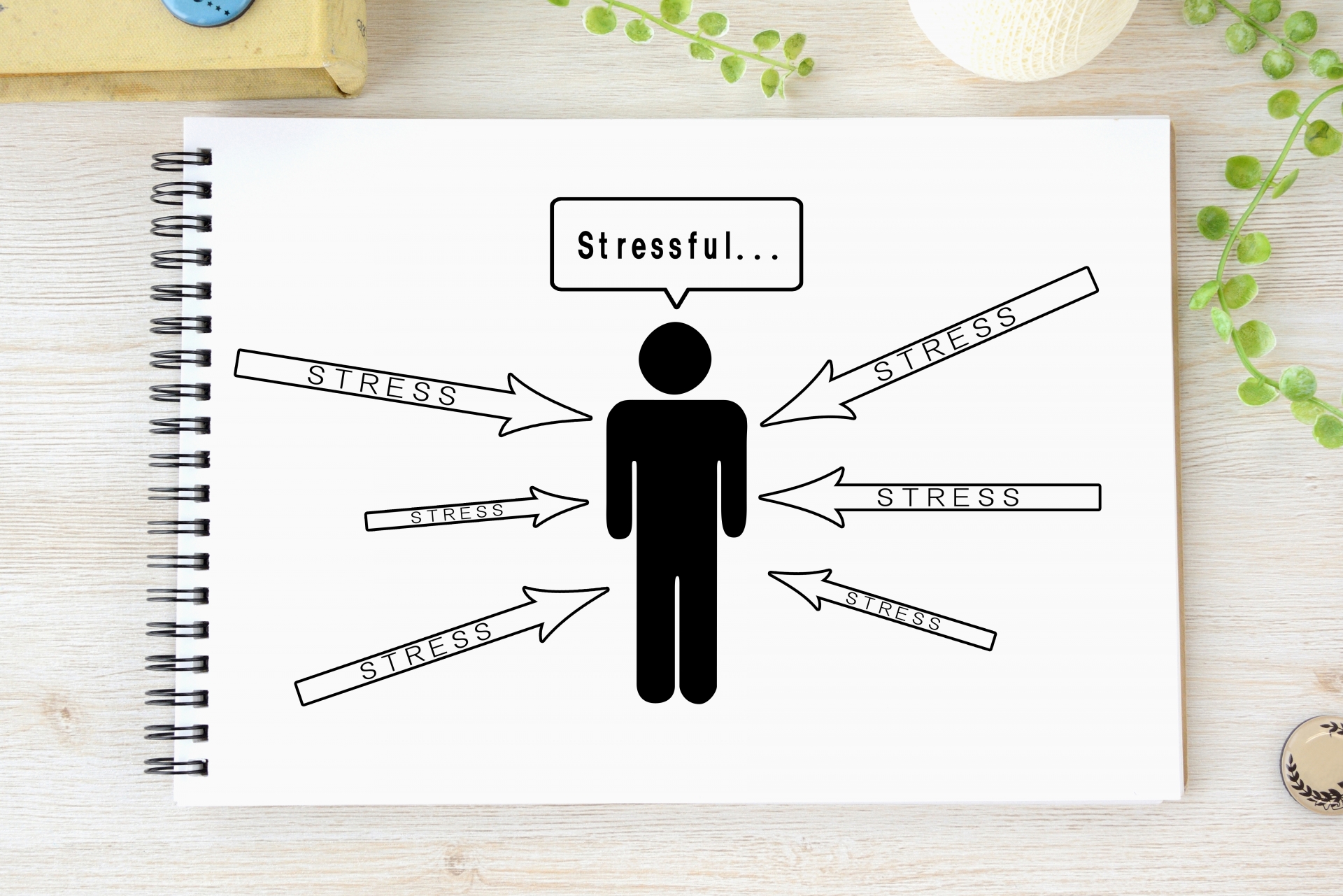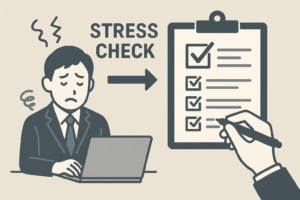目次
ストレスチェックって、企業にとって“義務”なの?
結論から言えば、従業員50人以上の事業所には年1回の実施義務があります。
義務の対象や、導入方法、結果の活かし方について、この記事で詳しく解説します。
ストレスチェック制度とは?
労働安全衛生法の改正により、2015年から導入された制度です。
目的は、従業員のメンタルヘルス不調の“予防”。
高ストレス状態を早期に把握し、必要に応じて面談や環境改善につなげることが求められています。
実施が義務になる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業所 | 常時50人以上の従業員がいる事業所 |
| 実施頻度 | 年1回以上 |
| 対象者 | 正社員・契約社員・パートなど、常時雇用の従業員全員 |
※産業医または医師による監修が必要です。
【図解】ストレスチェックの導入ステップ

実施の基本ステップ
- 社内準備(体制整備・対象者の確認)
- 実施(紙またはWEB)
- 集計・フィードバック(本人へ通知)
- 高ストレス者の面談勧奨
- 集団分析(部署別傾向の把握)
- 職場環境改善のアクションへ
よくある質問(Q&A)
Q. 面談を拒否されたらどうする?
A. 面談の受診は「義務」ではなく「勧奨(おすすめ)」です。
本人の意思が最優先されます。
Q. 小規模な部署でも実施は必要?
A. 対象は「事業所単位」で判断されます。
1つの拠点に50人未満でも、本社や他拠点と合算して50人以上の場合は義務になります。
Q. 集団分析とは?
A. 個人情報を除いた部署単位の傾向分析です。
ストレス要因を部門ごとに把握し、職場改善の指針とするものです。
結果を“活かせてこそ”意味がある
ストレスチェックは“やればOK”ではありません。
以下のように、結果を活かす仕組みづくりが重要です。
- 高ストレス者には適切な対応を
- 全体傾向から課題を抽出し、働きやすさを改善
- 年ごとの変化も分析して、継続的な対策へ
まとめ|義務だから、ではなく“企業の支援姿勢”として
ストレスチェックは、企業が“従業員のこころに関心を持っている”ことを示す施策です。
やらされ感のある対応ではなく、社員との信頼関係を築く手段として取り組むことが、健康経営にもつながります。