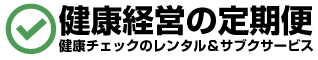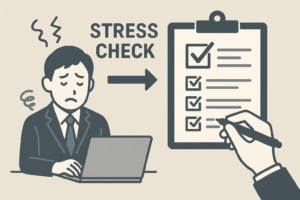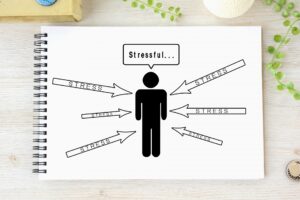目次
生産性に潜む見えないリスク「プレゼンティーイズム」とは?
社員の欠勤(=アブセンティーイズム)はすぐに把握できますが、
実は“出勤しているのにパフォーマンスが落ちている状態”=プレゼンティーイズムのほうが、企業の生産性に与える影響は深刻です。
プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの違い
| 用語 | 意味 | 影響の特徴 |
|---|---|---|
| アブセンティーイズム | 病欠・有給・私用などで仕事を休む状態 | 欠勤日数などで測定しやすい |
| プレゼンティーイズム | 出勤しているが体調不良・精神的な問題によりパフォーマンスが低下している状態 | 表面化しにくく、放置されやすい |
なぜ“プレゼンティーイズム”が問題なのか?
- ✅ 本人が「出勤している」ため周囲も気づきにくい
- ✅ 本人も“働いているつもり”なので危機感が低い
- ✅ 長期的に見ると生産性の低下・人材の疲弊・離職リスクにつながる
主な原因と背景
| 原因 | 具体例 |
|---|---|
| 慢性的な体調不良 | 睡眠不足、頭痛、腰痛、花粉症、PMSなど |
| メンタル不調 | ストレス・不安・うつ状態 |
| 職場環境・人間関係の問題 | ハラスメント、コミュニケーション不全 |
| モチベーション低下 | 業務過多・評価不安・成長実感の欠如など |
【図解】両者の違いと企業対応の方向性
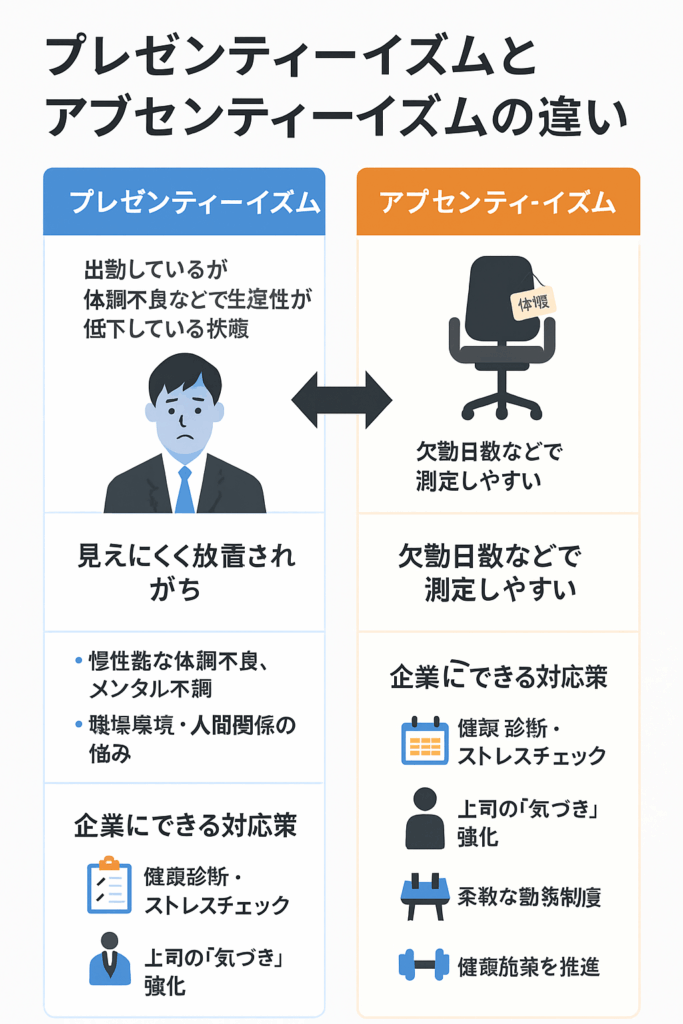
企業ができる対応策
① 健康診断・ストレスチェックの活用
プレゼンティーイズムの兆候は数値に現れにくいため、定期的なチェックと面談で“兆し”を早期発見。
➡ ストレスチェック制度の活用が有効
➡ 厚労省資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
② 上司・人事による「気づき」の強化
- 日頃の様子・表情・言動に気を配る「ラインケア」
- 年1の面談ではなく、月1の雑談が予防に効果的
③ 柔軟な勤務制度・リモート環境の整備
- 体調に合わせた時差出勤・在宅勤務の許可
- 無理をさせず、早めの休息を促せる体制づくり
④ 社員参加型の健康施策で「予防」
- 健康測定イベント
- 運動・ストレッチ習慣
- 食生活改善・禁煙支援 など
➡ 健康行動が日常にあれば、プレゼンティーイズムは大きく減らせます。
よくある質問(Q&A)
Q. プレゼンティーイズムはどうやって測る?
A. 主に自己申告制のアンケートや業務成果の変化、上司のヒアリングなどから判断されます。数値化は難しいですが、「傾向」を掴むだけでも大切です。
Q. 中小企業でも対策できますか?
A. はい。ストレスチェック・面談・フリーアドレス制度など、小さな取り組みの積み重ねが効果的です。
まとめ|“見えない不調”への気づきが健康経営のカギ
- プレゼンティーイズムは見えにくい損失
- 「働いているようで、働けていない状態」をどう見つけるかが重要
- 気軽に相談できる社内環境+予防的な健康施策で、企業のパフォーマンスも向上します