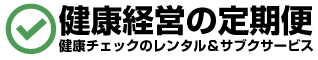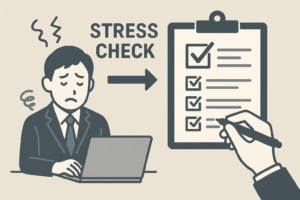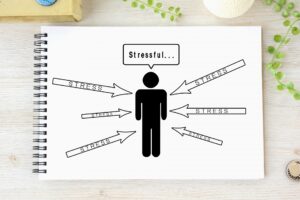目次
健康診断の結果、そのまま渡して終わっていませんか?
「健康診断は毎年ちゃんとやってるし、結果は本人に渡しているから大丈夫」
そんな企業も多いのですが、実はそれだけでは法的・実務的に不十分なケースもあります。
健康診断後に企業が行うべきこと
健康診断の実施には、結果を活用した“事後措置”がセットになっています。
企業が取るべき主な対応は以下の通りです:
- ✅ 結果の確認(所見のある社員を把握)
- ✅ 医師からの意見聴取(必要時)
- ✅ 労働時間・業務内容の見直し
- ✅ 本人への指導や配慮
- ✅ 必要に応じて産業医面談の設定
【図解】健康診断後の流れとフォローアップ
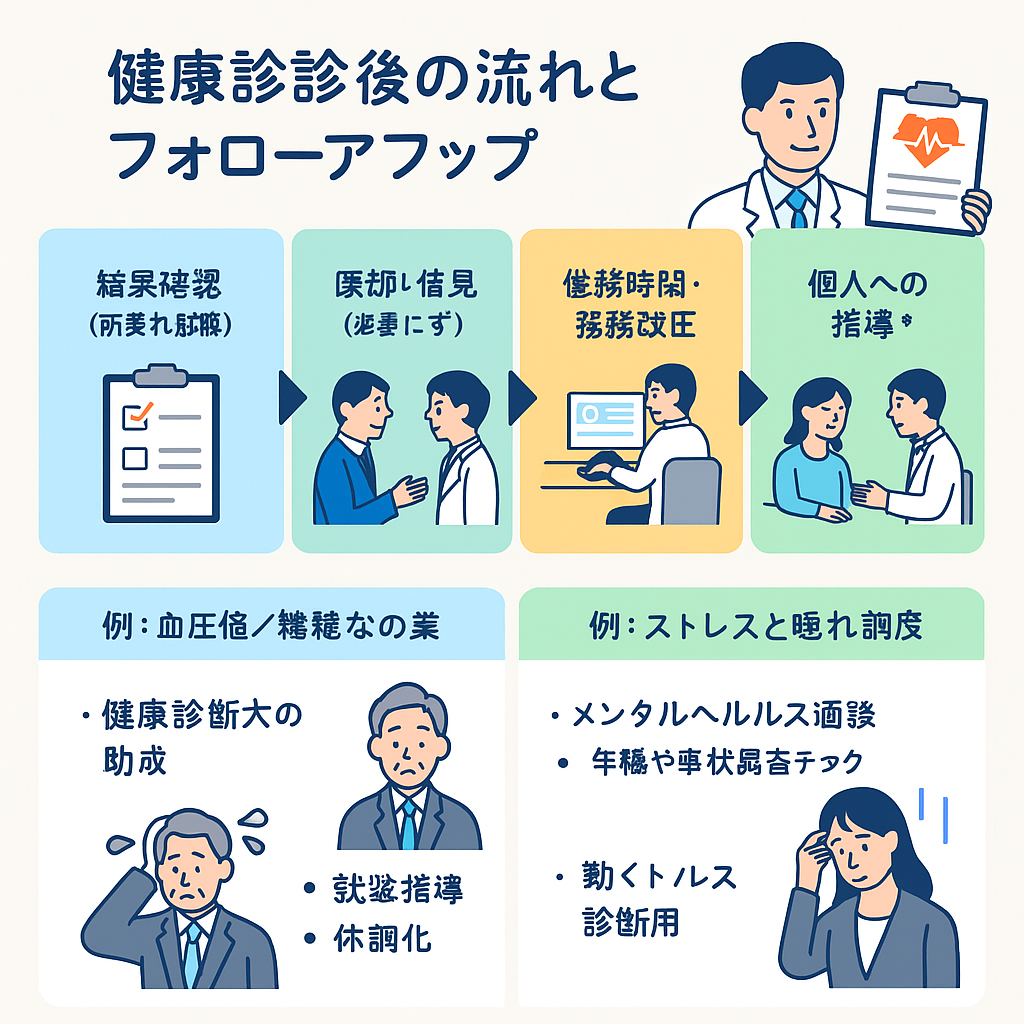
フォローアップの具体例
🩺 ケース①:血圧・血糖値が高い社員への対応
- 健康保険組合の「保健指導」を案内
- 定期的な医療機関受診を促す
- 就業時間内に保健指導時間を設定する企業も
💬 ケース②:ストレス・睡眠に関する所見があった場合
- メンタルヘルス面談や簡易ストレスチェックの再実施
- 必要に応じて勤務時間の柔軟化などを検討
よくある質問(Q&A)
Q. 結果の内容まで企業が確認していいの?
A. 健康診断の結果には個人情報が含まれますが、事業者にも確認・管理の義務があります。
ただし、取り扱いには十分な配慮(保管・閲覧制限)が必要です。
Q. フォローアップは産業医がすべき?
A. 法的には、医師の意見聴取や面談は「産業医」が推奨されますが、嘱託医でも対応可能です。
企業によっては健康支援事業者に委託しているケースもあります。
Q. 体調不良があっても本人が放置している場合は?
A. 本人の自己判断に任せるのではなく、会社側が定期的に声かけ・確認を行うことが重要です。
ただし、強制的な受診などはできません。
まとめ|“診断”だけで終わらせない健康支援を
健康診断は、ただの「義務」ではなく、従業員の健康課題を可視化するチャンスです。
診断結果を適切に活かし、信頼と安心を築くフォローアップ体制をつくっていきましょう。