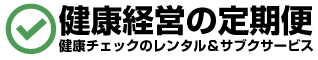目次
「歩きスマホ」は職場でもリスクになる
スマートフォンを操作しながら歩く「歩きスマホ」。
通勤中や街中での問題と思われがちですが、
実は職場内でも転倒事故の要因となりつつあります。
特に工場、倉庫、病院、オフィスなど、
“動線”と“注意力”が交差する場面では、
一瞬の油断が大きな事故に直結します。
なぜ歩きスマホが危険なのか?
厚生労働省によると、注意力の低下は労働災害の主要因の一つ。
歩きスマホは、視覚・聴覚・認知すべてを分散させてしまい、
転倒や接触、物損などの事故を引き起こすリスクがあります。
✔ 具体的なリスク
- 通路にあるコードや段差に気づかず転倒
- 人とすれ違う際にぶつかる
- エレベーターの乗降時にバランスを崩す
- スマホに気を取られて滑りやすい床に気づかない
職場で実際に起きた事例
✅ 医療施設での事例:
看護師が移動中にスマホを確認 → 点滴スタンドの脚に足を引っかけて転倒✅ 物流倉庫での事例:
作業アプリ操作中に段差に気づかず転倒 → 軽度の捻挫
このように、業種を問わず「ながら歩き」による事故が発生しています。
未病の視点から見る「注意力の低下」
「未病」とは、健康と病気の中間状態。
注意力の低下もまた、ストレス・睡眠不足・眼精疲労などが蓄積した未病状態のサインです。
職場では、こんな兆候が見られることがあります:
- 集中力が続かない
- 疲れやすい
- ミスが増える
- ぼんやりする時間が長くなる
このような状態でスマホに頼ると、事故のリスクがさらに高まるのです。
健康経営として取り組むべき歩きスマホ対策
企業としては、「禁止」だけでなく行動設計と環境整備が重要です。
① ルールの明文化と周知
- 職場内での歩きスマホ禁止をポスター等で明示
- 会議・休憩中などに注意喚起を徹底
- 業務用スマホの使用ルールを整備
② 行動設計の工夫
- スマホ操作は「立ち止まって操作」が前提
- 情報確認用の掲示板や共有端末を設置し、スマホ使用頻度を下げる
- スマホ使用スポット(ベンチ横・作業台等)を限定的に設ける
③ 健康測定×注意力チェックの導入
- 定期的に脳年齢チェック・ストレス計測などを導入し、注意力の変化を可視化
- 未病チェックとセットで“気づき”を促す
よくある質問(Q&A)
Q. 業務にスマホやタブレットを使う職場ではどうすべき?
A. 完全に禁止ではなく、「使う場所」と「使わない場所」の明確なルール化が必要です。
動線や作業エリアでは立ち止まって操作、閲覧専用端末の設置も効果的です。
Q. 歩きスマホの対策は“健康経営”と関係ありますか?
A. はい。注意力の低下は未病・ストレス・疲労のサインです。
転倒事故を未然に防ぐ観点からも、健康経営の一環として取り組むべきテーマです。
まとめ|「ながら歩き」は事故の入口
- 歩きスマホは職場でも転倒リスクを高める行為
- 未病の状態では注意力が低下しやすく、さらに危険
- 健康経営として、注意喚起+環境整備を進めよう
安全な職場は、足元と“ながら”の意識から生まれます。