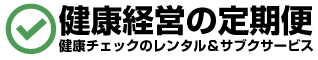目次
「転倒事故は“靴選び”から始まっている」
転倒事故の原因というと「段差」「配線」「床の濡れ」など環境面が注目されがちですが、
実は見落とされやすい要因のひとつが“靴”の問題です。
靴は足元の“インフラ”。
サイズや形状が合わなかったり、ソールがすり減っていたりすると、
転倒のリスクが一気に高まります。
靴が原因で起きる主なリスク
✔ サイズが合っていない
- 大きすぎる → 足が靴の中で動いて不安定に
- 小さすぎる → 足の動きが制限されバランスを崩しやすい
✔ 靴底がすり減っている
- グリップ力の低下 → 床で滑りやすくなる
- 段差で引っかかる → つまずきの原因に
✔ 紐を結んでいない・サンダル等の使用
- 歩行中に脱げたり、バランスを崩す恐れ
- 業務中はかかとの固定された靴を選ぶべき
厚労省も警鐘|靴の選び方と管理がカギ
厚生労働省の転倒災害防止資料でも、以下のような靴の管理が推奨されています:
- 靴底のグリップ力とすり減り具合の点検
- 靴ひもタイプならしっかり結ぶ
- 職種に応じて、安全靴・滑り止め付きの靴を選ぶ
- 私物靴の使用制限や貸与制度の検討
健康経営・未病対策としての「靴の見直し」
「未病」の段階では体のバランス感覚や筋力が微妙に低下し始めており、
その変化は見た目ではわかりません。
こうした未病層の従業員が不適切な靴を履いていると、
わずかなつまずきが重大事故に直結するおそれがあります。
➡ 靴の定期点検や履き替え促進は、企業の安全対策の一環として重要です。
職場でできる靴対策の具体例
① 靴の点検・交換の声かけ
- 半年に1回の「靴チェック週間」の実施
- 安全大会などで靴の重要性を啓発
② 企業による靴の選定・貸与
- 立ち仕事・製造業では「職場指定の安全靴」の導入
- オフィスワークでも滑りにくい屋内用シューズを推奨
③ 健康チェックと靴チェックの連動
- 健康測定会とセットで靴底の確認
- 足元撮影・摩耗具合の記録など可視化の工夫
よくある質問(Q&A)
Q. 職場で個人の靴まで指導するのはやりすぎでは?
A. そう感じる方もいるかもしれませんが、
「安全のために必要な配慮」としての位置づけを伝えることで納得感が得られます。
特に転倒事故が起きた職場では、再発防止策として必須です。
Q. 高齢の従業員が転倒しやすくなっています。対策は?
A. 年齢とともに足の筋力や感覚は低下します。
高齢層にはかかとがしっかり固定され、クッション性のある靴を推奨すると良いでしょう。
また、「靴を履くのが面倒だからサンダルに」というケースも注意が必要です。
まとめ|転倒予防は“足元”から始まる
- 靴は転倒予防の最前線
- 小さなすり減りが事故につながる可能性も
- 健康経営の一環として、靴のチェック体制を職場に根づかせよう
足元を整えることが、職場の安全を守る第一歩です。