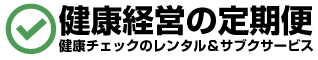目次
小さな段差が転倒事故を招く?
段差と聞いて、どのくらいの高さをイメージしますか?
5cm?10cm?
実はたった2cmの段差でも、重大な転倒事故につながることがあります。
「つまずき」はなぜ起こるのか?
人の歩行は無意識の動作で行われています。
そのため、床の高さが少しでも変わると——
✅ 足がひっかかる
✅ 歩幅が乱れる
✅ バランスを崩して倒れる
こうした事故が簡単に発生してしまいます。
実際に起きた事例(厚労省より)
- 事例①: 休憩室の入口の敷居(約3cm)でつまずき、肘を骨折
- 事例②: 古い建物の通路の沈み込み部分でつまずき、顔面を強打
- 事例③: トイレと廊下の境目で段差につまずき、腰を強く打って長期離脱
どの事例も、「段差があるのは知っていた」のに意識しなかった・慣れていたという理由で防げなかったのです。
「未病」の視点から見る段差の危険
“未病”とは、健康と病気の間のグラデーション。
これを職場環境に置き換えると、次のように考えられます:
✅ 明らかに危険な状態ではないが
✅ 小さな違和感や変化がある状態
段差もまさに、「事故になっていないけど放置されがちな未病状態」の一例です。
健康経営の観点からの段差対策
健康経営においては、従業員の安全・安心も企業の責任とされます。
段差による転倒を防ぐことは:
- 従業員の健康維持
- 離脱リスク・労災リスクの低減
- 精神的安全性の向上
に直結します。
✔ 実践すべき段差対策
- 段差解消スロープの設置(3cm以下でも有効)
- 黄色ラインや注意ステッカーで視認性アップ
- 段差付近に「足元注意」のポップや掲示
- 夜間や倉庫など照明の弱いエリアの照度改善
✔ 日常の点検項目
- 古い建物や仮設レイアウトの床段差
- マット・カーペット・養生テープの盛り上がり
- ドア枠や出入口など「自然発生的な段差」
- 季節的に変化する床の浮きや反り
よくある質問(Q&A)
Q. 何cmの段差から対策が必要ですか?
A. 一般的には2cm以上がつまずきのリスクラインとされていますが、1cmでも繰り返し起こる場所なら対策すべきです。
Q. 段差を完全に解消できない場合はどうすれば?
A. スロープや目立つ表示での対策が有効です。
特に高齢者や体調不良時に転倒しやすくなるため、視認性を高めるだけでも大きな効果があります。
まとめ|“段差”に気づける職場が、事故を防ぐ
- 段差は「当たり前」になりやすい職場の未病ポイント
- 小さな段差でも大きな事故につながるリスクあり
- 点検・改善・声かけを通じて、気づきと対策を習慣化することが大切
足元の“ほんの少し”が、企業と従業員の未来を変えるかもしれません。