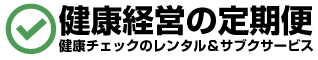目次
床の“たわみ”が招く、意外なリスクとは?
「転倒」と聞くと、濡れた床やコード類の放置を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実は、床の“たわみ”や沈み込みといった、目立たない劣化も転倒事故の引き金になっています。
なぜ床のわずかな変化が危険なのか?
一見しただけでは気づきにくい「たわみ」。
しかし人は、予想していない“沈み込み”に足を取られると、バランスを崩しやすくなります。
✅ 特に高齢者や足腰が弱っている人にとっては致命的な転倒リスク
✅ 不意に足を取られた際に反射的に体を支えようとして腰や膝を痛める事例も
✔ たわみが起こりやすい場所の例
- 長年使用されているカーペット床の一部
- 重機・什器が頻繁に置き換えられる場所
- 水分や湿気を含みやすい床材(キッチン・洗面スペース)
- 配線や配管の上に置かれた床板の継ぎ目
“たわみ”は職場の「未病」状態?
私たちはよく「未病=体の不調の前兆」として使いますが、
実はこれは職場環境にも当てはめることができます。
✅ 床のわずかな沈み込み
✅ 壁の小さな亀裂
✅ 換気の効率が落ちている
こうした「まだ事故になっていないけれど、兆しがある」状態を“職場の未病”と考えることができます。
健康経営における職場環境の管理
経済産業省が推進する健康経営では、
「職場の安全と快適性」も従業員の健康の一部として捉えています。
✔ 健康に働ける環境=企業の価値
- 転倒による労災やケガのリスクを減らせる
- 従業員が安心して仕事に集中できる
- 離職やモチベーション低下を予防
厚労省が示すチェックポイント
厚生労働省の安全衛生対策では、次のような定期チェック項目が推奨されています:
- 床材の劣化(沈み・きしみ・波打ちなど)
- カーペットやマットのズレ・めくれ
- 滑りやすい材質の使用箇所の把握
- 水回りや段差周辺の滑り止め対策
対応策は「点検+記録+共有」
① 月1回の職場点検を実施
- 安全衛生委員会・総務・施設管理者などが目視+踏みごたえをチェック
② 劣化・異常はすぐ記録
- 撮影+記録して定期改善リストへ
③ 従業員にも共有
- 「この場所は注意してください」と周知するだけでも事故は減らせます
よくある質問(Q&A)
Q. 古い建物でも健康経営って実現できますか?
A. はい、建物の新しさではなく「気づいて改善する体制」が重要です。
ちょっとした補修や点検・張り替えをコツコツ積み重ねることが大きな事故を防ぎます。
Q. たわみや沈み込みの判断基準はありますか?
A. 「足を乗せたときに不安定・沈む・ギシギシ音がする」は要注意サインです。
違和感を覚えたら、写真+位置情報で記録しておきましょう。
まとめ|床の“未病”を見逃さない安全管理を
- 床のたわみ・沈み込みは転倒の大きな要因
- 職場の“未病”を見逃さない意識が、健康経営の出発点
- 点検・記録・共有を定着させて、事故ゼロを目指しましょう
見えない“足元の危険”こそ、先回りして守るべきです。