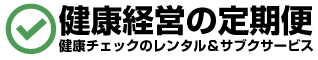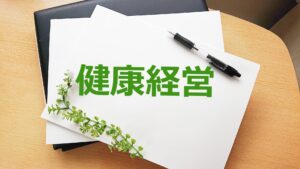健康経営は「気づき」から始まる
健康経営というと、福利厚生の充実や健康診断、スポーツイベントなどの施策を思い浮かべる方が多いかもしれません。
もちろんこれらは大切ですが、本質的な健康経営の第一歩はもっとシンプルなところにあります。
それは——
「従業員のちょっとした変化に、誰かが気づける職場であること」です。
「未病」という視点を活かす
神奈川県が推進する「未病(みびょう)」という概念をご存じでしょうか?
未病とは、「病気ではないが健康ともいえない状態」を指す言葉です。
たとえば:
- 最近疲れやすい
- なんとなく調子が出ない
- 集中力が続かない
- 表情が冴えない
これらは病気とは診断されませんが、健康から遠ざかっているサインかもしれません。
未病のまま見逃されると…
未病は本人が気づいていなかったり、
気づいても「まだ大丈夫」と放置されやすいのが特徴です。
しかし放置しておくと、次のようなリスクに発展することがあります:
- パフォーマンスの低下(プレゼンティーイズム)
- メンタル不調・離職
- 重大な健康障害(アブセンティーイズム)
つまり、健康経営の目的は“病気になる前に手を打つこと”とも言えるのです。
職場でできる「気づきの仕組み」
では、どうすれば未病の兆候に気づける職場をつくれるのでしょうか。
✔ 日常のコミュニケーションを大切に
- 朝の挨拶や雑談で表情や声のトーンをチェック
- 「最近どう?」の一言がきっかけに
✔ 上司・管理職が“観察力”を持つ
- 面談や1on1で生活リズムや健康状態にも触れる
- 「無理していないか」に目を向ける
✔ 健康測定やストレスチェックを定期実施
- 見えない変化を“数値化”して気づきを促進
- 身体と心の両面を把握する仕組みづくり
健康経営は“気づいたあと”が勝負
気づきだけで終わらせないためには、
「声をかけられる・相談できる・フォローできる」体制づくりが必要です。
✅ 体調不良時に柔軟に休める風土
✅ 保健師・産業医・外部相談窓口の活用
✅ 上司・同僚の理解と寄り添い
これらがあることで、従業員は安心してケアを受けられ、結果的に職場の活力が向上します。
経済産業省も推進する「健康経営」
経産省が選定する「健康経営銘柄」では、
企業の健康投資への積極姿勢が高く評価されます。
単なる施策の数ではなく、
「職場全体で健康に向き合う文化があるか」が問われるのです。
よくある質問(Q&A)
Q. 小さな会社でも健康経営は可能ですか?
A. もちろん可能です。
重要なのは「制度の有無」ではなく、人のつながりによる“気づき”と“行動”。
小規模な職場ほど、個々に目が届きやすく、柔軟な取り組みがしやすい利点があります。
Q. 未病のサインにどう対応すればいい?
A. 定期的な健康測定や産業医面談を活用し、早めのケア・相談・休養が大切です。
「何かおかしいかも?」の時点で対応することで、重症化を防ぐことができます。
まとめ|健康経営は「未病」に気づく職場から
- 健康経営の出発点は「変化への気づき」
- 未病という視点が、従業員の健康を守るヒントに
- 小さな声に耳を傾けられる職場こそ、健康経営の土台
まずは、“気づく力”を育てることから始めましょう。