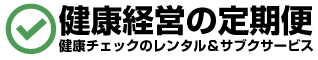目次
ロコモとは?「立つ・歩く」がつらくなる未病のサイン
ロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)とは、
骨・関節・筋肉など運動器の衰えによって、移動能力が低下する状態を指します。
高齢者だけでなく、働き盛りの世代でも“運動不足”や“生活習慣の乱れ”により、
未病の段階でロコモが始まっていることも少なくありません。
足の筋力低下が転倒を引き起こす
足腰の筋力が落ちると、以下のような状態に陥ります。
- 歩幅が狭くなり、足を上げにくくなる
- 踏ん張る力が弱まり、つまづきやすくなる
- 段差への反応が遅くなる
- バランスを崩したときに耐えられない
➡ 結果として、転倒・骨折のリスクが急増します。
ロコモ対策は「未病改善」と「転倒予防」の両立策
ロコモは、進行すると要介護状態へつながるリスクがあります。
しかし、未病の段階であれば、対策次第で回復・改善が可能です。
厚生労働省でも、「ロコモティブシンドロームの予防」を
中高年の健康施策の中心として推進しています。
職場でできる簡単ロコモチェック
- 片足立ちが10秒未満
- イスからの立ち上がりに手を使う
- 歩く速度が遅くなったと感じる
- 小さな段差につまづく
- 疲れやすくなった
➡ 1つでも当てはまれば、ロコモ初期のサイン(未病)かもしれません。
職場で実践できるロコモ対策
① 下肢筋トレの習慣化
- スクワット(浅めでOK)
- カーフレイズ(かかとの上げ下げ)
- 椅子を使った片足立ちトレーニング
これらを1日5分でも続けるだけで、筋力維持に効果的です。
② 動く機会を増やす職場環境
- エレベーターではなく階段を推奨
- 昼休みにウォーキングタイムを設ける
- デスクワーク中にもストレッチや立ち作業を取り入れる
③ 社内イベントや掲示物による啓発
- 「1日10分運動チャレンジ」などのキャンペーン
- ポスターや掲示で“ロコモ予防”を可視化
- 健康経営レポートでロコモ対策を明記
よくある質問(Q&A)
Q. ロコモは若い人にも関係ありますか?
A. はい。運動不足の20代〜30代でもロコモ予備軍になり得ます。
特に座りっぱなしの職種では注意が必要です。
Q. ロコモ対策と健康経営はどう結びつくの?
A. ロコモ予防は、従業員の活動性・生産性を高める施策です。
また、転倒事故の予防にもつながるため、健康経営の一環として推奨されます。
まとめ|足腰の衰えに気づいたら“今”が対策のタイミング
- ロコモは未病段階で気づくことが最も重要
- 足の筋力低下は転倒や要介護の入口
- 職場でもできる小さな工夫が、将来の健康を大きく左右します
「立つ・歩く」が当たり前であるために、今こそロコモ対策を始めましょう。