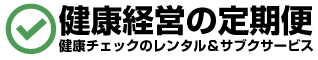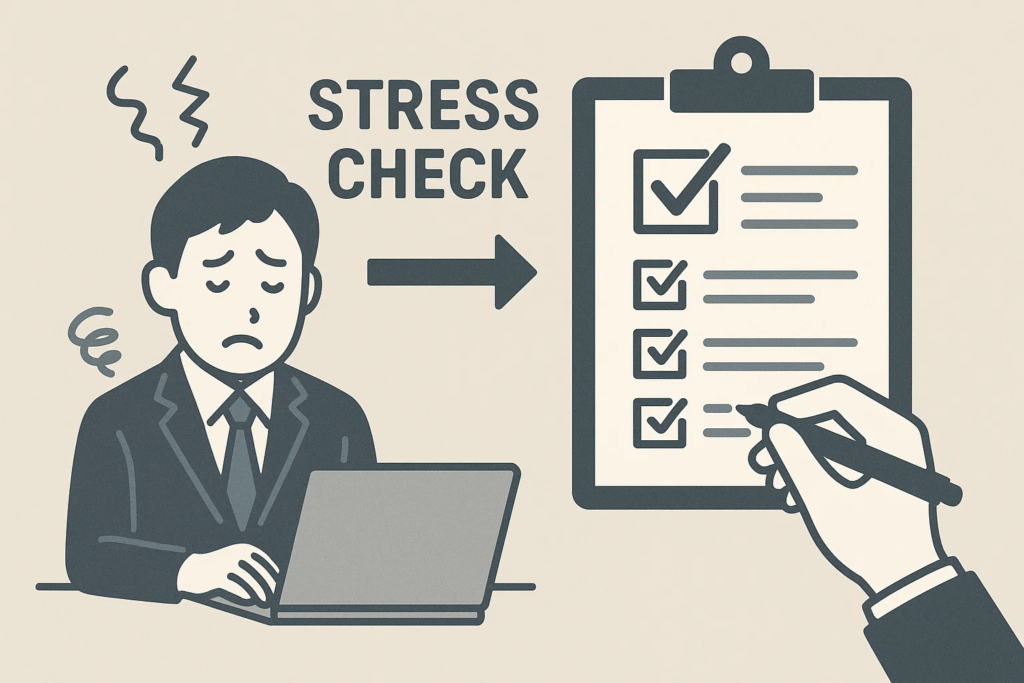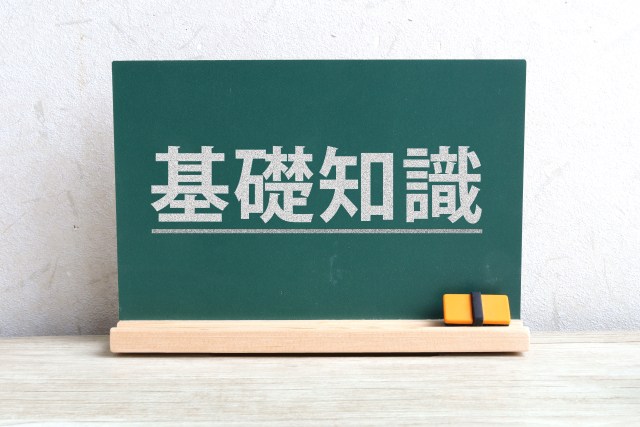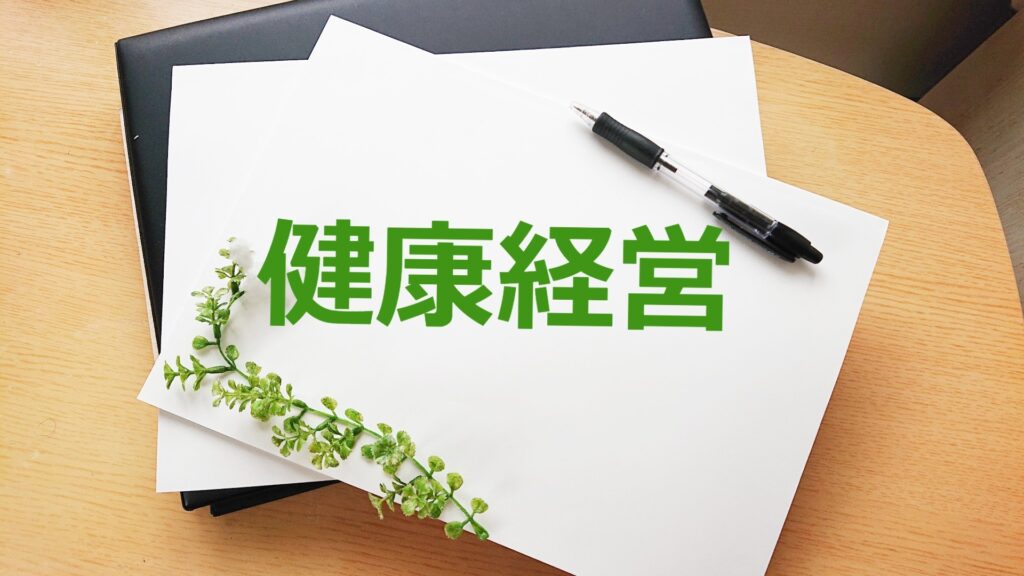2025年– date –
-

健康経営を盛り上げる!健康測定機器を活用した社内イベント成功事例
■ 社内イベントは健康経営を「体感」させるチャンス 健康経営の取り組みは、制度やルールだけではなかなか浸透しません。そこで効果的なのが、健康を体験できる社内イベントです。 特に、健康測定機器を社内に常設し、イベントと組み合わせることで、「楽... -

従業員の健康維持に効果的!日常的な健康フォロー方法とは
■ 日常的な健康管理が企業を強くする 健康経営を進める上で最も重要なのは、従業員の健康を日常的にフォローし、管理することです。健康測定機器の導入は、従業員一人ひとりの健康状態を可視化し、早期に問題を発見する手助けとなります。その結果、病気や... -

オフィスに「健康測定スペース」を!健康経営を支える常設施策のすすめ
■ 健康経営を“形にする”職場環境づくり 健康経営を掲げる企業は増えていますが、実際に従業員が「健康に取り組める環境」がなければ定着しません。その鍵となるのが、オフィス内に健康測定スペースを常設する施策です。 健康を“体験”できる場所をつくるこ... -

健康経営を社内に根付かせる!実践企業が行う「仕組み化」のポイント
■ 「やって終わり」にしない健康経営へ 健康経営の取り組みは、最初の意欲は高くても、数か月後には形骸化してしまうケースが少なくありません。その理由は、仕組みとして定着していないことにあります。 経営層のコミットメントだけでなく、現場で自然に... -

いまさら聞けない「健康経営」とは?企業に求められる“健康投資”の新常識
■ 健康経営とは? 「健康経営」とは、従業員の健康を経営資源と捉え、組織の生産性向上や企業価値向上につなげる考え方です。経済産業省と日本健康会議が推進しており、優れた企業には「健康経営優良法人」として認定を受ける制度も整備されています。 従... -

健康診断だけでは足りない?日常的な健康チェックの重要性とは
健康診断だけで本当に大丈夫? 多くの企業では、年1回の健康診断を実施して従業員の健康状態を把握しています。しかし、健康診断だけでは日常の不調や兆候を見逃す可能性があります。 健診結果が正常でも「未病状態」のケースがある 年1回では変化に気づき... -

社員の“未病”を防ぐ!日常でできる健康チェックの仕組みづくり
■ 健康チェックは「年1回」から「毎日できる」へ 多くの企業では、健康診断が年に1回だけ行われています。しかし、生活習慣やストレスの影響による“未病”の変化は日々起こるもの。年1回のデータだけでは、体調の変化を見逃してしまう可能性があります。 そ... -

従業員の転倒リスクを“未病”で防ぐ。職場でできる3つの対策
転倒はすべての従業員に起こり得るリスク 転倒事故は高齢者だけのものではありません。すべての年代の労働者に潜む職場リスクとして、厚生労働省も注意を呼びかけています。 特に、未病の段階で現れる「ふらつき」「疲労」「集中力の低下」などは、転倒の... -

“健康投資”が企業価値を高める。経産省が示す新しい経営のカタチ
健康経営は“投資”である 従業員の健康施策にかける費用を、「コスト」ではなく「投資」と捉える——それが、経済産業省が推進する健康投資の概念です。 この視点は、健康経営を一過性の取り組みではなく、企業価値を高めるための中長期戦略として捉えるヒン... -

“未病”に気づける社員を育てる。健康リテラシー向上の職場づくり
健康経営の核心は「社員の気づき」 健康経営というと、健康診断やイベント施策が注目されがちです。しかし、本当に重要なのは—— ✅ 従業員自身が「自分の体調変化」に気づける力✅ 日常の中で“未病”に対して先回りできる感覚 いわゆる「健康リテラシー」の育...